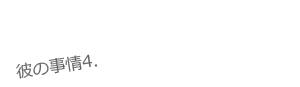
彼は焦っていた。
いつかのようにずんずんと廊下を進み、引っつかんだ一枚の書類を持ってことの顛末を知るのに必死だった。
まず、むかったのは、彼女の直属の上司、自分の部下のところだった。最近、胃潰瘍になったとの噂だが、彼は知ったこっちゃ無い。
脂汗をかくそいつの胸元を掴み上げ、おなじみの雄たけびを挙げて脅せば、
その上司はあわや、片手で胃を押さえ、もう片手で器官を守るために彼の腕に掴まった。そんな状態じゃ、しゃべれるものもしゃべれない。
もし、胃痛に苦しむその部下に度胸と“人生もうどうでもいいや”という覚悟があったら、しゃべれねぇよ!と、そう言ってただろう。
呻いて青くなり始めた彼女の上司をスクアーロは無慈悲にも地面へほうりなげ、彼が、咳き込みながらも喋った内容に瞠目した。
「ゲホッガッ…ウエ……彼女たっての申請だったんです。…もうこの人ヤダ…」
いい年も差し掛かった彼女の上司は自分の弱音も織り交ぜつつ、そう言った。申請?スクアーロは、呻くそいつを再び持ち上げる。
「誰の許可でそんなことをしたぁ゛!!」
だから、しゃべれねぇって!
誰か、ヒートアップしている彼にそのことを伝えてやってほしい。
彼女の上司の顔はすでに土気色である。再び地面と熱いおしくらまんじゅうを(一方的)した彼は、ふらふらしながら言った。
あの…ベルフェゴール隊長とマーモン隊長の認可がありまして…
自分ではどうにも…できませんでした…スクアーロ隊長には言うなって言うし…グスン
その瞬間、スクアーロに嫌な電流が走る。
それは、一瞬だったがあの二人の悪魔のような笑みが、まざまざと思い返された。彼の心中はこうだ。
やっぱりしでかしてくれた!
「あ゛?だが、彼女たっての…って言ったよなぁ゛?」
「はいそうです!」もう掴ませる襟はないですよ!と胸元を握りしめた上司は、妙にキラキラとした笑顔で言った。
それが彼の癪に障った。
その後に、なにやら喋っていたようだが、苛立った彼の、隼のごとしミネウチで、昏倒し強制的に沈黙せざる終えなくなった。
なんというか、
これは犬は飼い主に似るという現象なのだろうか。物を投げまくるスクアーロの上司の「カス!」と言う姿が浮かんでは消えた。
そして、地面に伏している男の姿など目もくれず、彼は歩きだした。出口へと。
申請とかもう、どうでもいい。
彼は歩いていた。もう、走っていたと言ってもいいだろう。彼は考える。
彼女の事情を。
因みに、彼の想像のなかで、彼女はもう、日本の天然記念物「大和撫子」をも凌駕する、
もう、一種の天使のような無垢な存在となりつつあった。
故に、彼の中の彼女の事情は、壮大なストーリーとなる。
スクアーロは思う。
彼女はきっと、なにか大金のいる事情があるに違いない。あの強欲な赤ん坊と違ってもっと謙虚な。
例えば、両親が知人の借金の保証人となり、知人の逃亡、そして両親の不幸。
膨大となった身に覚えのない、借金の山。ジャッポーネマフィアに追われる日々。徐々に酷くなる生活。
それでも彼女は捨てられた犬やら猫やら子供(?)やら、きっと見捨てられない優しい心の持ち主だから、
それらも抱え込んで…
そしてついにどうしようもなくなったとき、その身を外国に売られてしまったのだろう。
けれど、そんな彼女の生き様に心打たれた優しい誰かが、彼女を逃がし、そして最終的にはこのヴァリアーの収入に引かれて就職…
ほんとうに想像にたくましかった。
文章でしたためると妙な誇張が入るにしても、あらかたこのようなストーリーが彼の脳裏に浮かんだのは確かだ。
ほんの少し潤んだ目をぬぐい、スクアーロはギロリと前を見据えた。
待ってろ!!必ず救ってやる!
そうして、彼は、単身、暗殺単独任務現地へと出発した。因みにこれは立派な無断退社であり、
彼の上司はそのことを知った瞬間、「カッ消す。」と死刑宣告をのたまったのだった。
おそらくもっとも救われるべきは、スクアーロだろうに。