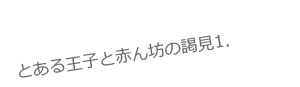
同僚とのコミュニケーションという名のいじめのあと、
二人の悪魔が粘写によって導かれた場所は、ヴァリアー本部になっている古城に設けられた中庭だった。
暗殺部隊の彼らが過ごすには、のどかで場違いな場所だ。
中心には噴水が設けられ、ソレを囲むように、今では自生しているバラやマリーゴールドが咲き誇る。
時々、晴れの守護者がその花の世話をしているらしいが、彼らには関係ない。
最短距離を通るため、なんの慈悲もなく彼らは踏み倒し進んでいく、そこに例の彼女はいた。
小柄でどこにでもいそうな風貌の女がヴァリアーの制服を纏い、石造りの椅子に腰をかけ、本を読んでいた。
当然、今は勤務時間中であるが、彼女は事務の仕事を早々と終えている。
しかも、殊勝なことに、上司にほかの仕事はないか、と尋ねたところ、
上司はしどろもどろに、冷や汗をかきながら、「事務以外はない、休憩でもしておけ、」と追いだされたところだった。
彼の圧力はこんなところでも彼女を振り回していた。なんという職権乱用。彼らのボスが知ったら全焼ものである。
もちろんスクアーロが。
さて、悪魔二人組みは、予想と違って、おとなしめでどうみても、ヴァリアーに相応しくない彼女の姿を遠めに見て、
そのうちの一人である切り裂き王子は独特の笑いを漏らし、今ではふてくされているだろう自分の同僚を思った。
アイツ、目でも腐ってんじゃねーの?さすがカス鮫。
この王子はどこまでもあの鮫に対して辛辣だった。
因みに、この切り裂き王子の女性のタイプは姫っぽい女。抽象的であるが、残念なことに彼女はどこからどうみても、
姫じゃなかった。姫というより姫のメイドとか、側近とか、そういうポディションらしい。
つまり、ベルのタイプに掠りもしかった。だから辛辣度2割り増しだったといえばそうだった。別に、期待はしてなかったけどな!とベルは言う。
「ねぇ、お前」
「はい?」
ぴらり、と一枚ページをめくった彼女をみたあと、王子はまったくその名に恥ずかしくない不遜な態度で彼女に話しかけた。
振り向いた彼女は、やっぱり事務っぽい普通の態度で「こんにちわ」と返してくる。せっかく背後から話かけたというのに面白くない。
ベルフェゴールは実は密かに腹を立てた。王子が声かけてんのに。
「お前がカス鮫の女?」
「カス鮫ですか?」
なんのことだか分かっていない彼女は、首を傾げながら本を閉じた。
もともと良くない印象をもっていたベルが、その時たまたま見たのは、本に備え付けられた紐の栞を抜け目なく挟む彼女の態度。
たったそれだけだったが、ベルは反応した。ふぅん、余裕じゃん?空気は一気に不穏な気配を見せる。
隣で見守っていたマーモンが、切り裂き王子の気配を察して、ベル、と窘めた。
「やめときなよ」
「?」
そこに居るのは、ただの普通の女だよ。マーモンが言う。
けれど、ベルフェゴールは、そのただの女が暗殺部隊のヴァリアーに居るというのも許せないのだ。
彼らは彼女の任務履歴を聴取済み。だからこそベルは思う。
暗殺部隊を名乗っておきながら、事務専門?戦えないなら、そこらの店で店番でもしてれば?なんでいんのお前。
自ら王子と名乗る彼は知っていたのだ、名前や肩書きの重さ、そしてわずか8歳で前線に立ち知ったヴァリアーの強さ。
だから、余計にこの悪魔の名前をかんするものが集まった地獄の集団で、まるで似合わない調和を乱す存在が無意識に許せなかった。
ベルフェゴール。切り裂き王子の故郷と家は、世界広しといえど、ここにしかないのだから。
「ねぇ、遊んでよ。暇してんだよね、俺。」
「ベル」
口の端がにぃっと上がる。
「断るわけないよね、俺、王子だし!」
そうして、ベルフェゴールの手から一つのナイフが放たれた。
***
同時刻、
あーあ、とマーモンは思っていた。きっとまた上層部が荒れる。
スクアーロは、お気に入りに手を出されたことを怒るだろうし、ベルフェゴールはその喧嘩をよろこんで買うだろう。
そして、その騒音にキレた上司の憤怒がその二人と屋敷を焼く。その喧騒に巻き込まれて、城の被害総額は200万くらいかな。
そんなお金があるなら僕にくれればいいのに。とマーモンは心のそろばんを弾く。
すごいところは、彼が、数秒後死ぬであろう彼女の心配をまったくしていないところだ。
さすがは赤ん坊でありながらヴァリアー。
そして、そのあと彼は思ったのだ。
“あのうわさ”は嘘か。
けれど、それを口にだすことなく、マーモンはことの成り行きを見つめ続ける。
***
飛んでいくナイフ。
ベルフェゴールは確信した。“あたる!”
狙いは勿論、左の胸。心臓の真上、ナイフの大きさからすれば、余裕で貫ける。
先輩、怒るかも。でも、しょうがないよな、事故事故。とベルは笑う。
しかし、二人のヴァリアー幹部の“一瞬先には地味な女のスプラッタ死体が横たわる”予想ははずれ、
放たれたナイフは受け止められた。
それは、銀髪の救出者が登場、
とかでは、なく、首をかしげている彼女本人の手によって。
彼女は受け止めた独特な形のナイフをまじまじと見つめ、
「え、遊ぶってなんですか?ダーツ?ですか?」
シュールな発言。
続けざまに、私ルールよくしらないんです。
非常に申し訳なさそうに言った彼女は、左手の人差し指と中指で投げられたナイフを挟み、
同時に、右手でこともなげに本をポケットにしまっていた。
二人はめずらしくも唖然。
しかし、あえて何度も言おう。ここは独立暗殺部隊、ヴァリアーである。
この地獄の園では、仏の顔すら悪魔の所業に違いない。
けれど、まるでそれを想像できない、庶民臭さが彼女の持ち味となるのは、これよりだいぶ後だ。
そして、様々な誤解と判明を孕みつつ、話は時間を少し進み、
彼女がAランク暗殺の任務に就いたことを彼が知った、そのあとに戻る。