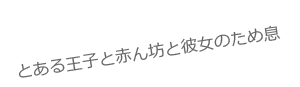
なぜが“かまいたち”の容姿は伝わってこないのか、目撃者だってこんなにもいるのに、皆そこは語らない。
疑問に思ったものが尋ねてみれば、ひとりの若者が震えながら、しかしどこか嬉しそうに、言った。
「速過ぎて見えなかったのさ。」
そして、それはまるで人知を超えた奇跡の話となった。
***
「そういや、なんで、“かまいたち”の姿って噂されなかったの?」
「口止め?」
「いやぁ…」
頬をかきながら彼女は思う。面倒くさいから。と。
任務が終わったその場で、彼女は目撃者達に収集をかけ、自分のことは周りに内緒にするようにと、『お願い』した。
“かまいたち”の実力を知った連中は首を縦に振るしかなかっただろう。彼女はそのあと、満足げに笑い、よろしくおねがいします。
といつものように深々と腰を折った。血塗れの刀さえなければ、本当にいいお辞儀だった。今の彼女の動作に親愛は生まれない。
それは恐怖が誕生するのみの動作だった。
どうして、そんなことをしたか。
それは、彼女が刀で戦う以外興味ないからだ。
刀対体術、刀対ナイフ、刀対その他、どれも惹かれない。
唯一敵同士、なが物を持っての刀対刀の決闘みたいな戦いが彼女は好きだった。
だから、話を聞いた者が訓練をつけてほしいと、彼女に頼みにくるのも、興味をもったものが戦って欲しいと血の気の多くふっかけにくるのも、
彼女には苦笑いして断ることになる。それなら、知られるまえに対策を取ってしまったほうがいい。
まさか初任務で、あんなにも目立つなんて思ってなかった彼女は、とりあえず、目撃した同僚に黙っているように頼んだのだ。
任務のあとも、書類の処理がしやすいことを理由に、ほかに任務に参加していた者の書類を集め、
自分について余計なことを書いてないかチェックしておいたほどだ。
まあ、目撃者は全員、約束を守ってくれていて、必要なかったけれど。
そして、彼女は快楽殺人者ではないと自負していた。また、戦闘狂でもない。いや、刀の決闘のみの戦闘狂か。
選択できることならば、(刀以外)戦いたくない。というのが彼女の心のうちだった。
まあ、だからといって事務でおさまるほど彼女は大人しいものじゃないので複雑だが。
余計な生ぬるい戦いをするのを嫌い、彼女は自分の姿を隠したのだ。
だが、結局“かまいたち”という別の、彼女の知らない、代理の名前が広がってしまった。
「じゃあアイツ相当馬鹿じゃね?」
きっと、例の彼はやわらかくて脆いものを守ってると勘違いしている。それはやわらかくも、まして脆くもない。
「あ、やっぱり仕事が事務ばかりなのってスクアーロ隊長の考えだったりしますか?」
「そうだね。」
「ぜってぇそう。」
おもわず、はぁーと彼女は息を吐く。やっぱりか。
「まったく金にならないことしてるよね。使えるものがあるんだから使えばいい。」
「カス鮫に言ったら?余計なことするなって」
「確信もなかったしなかなか言い出せなくってですね…ずるずるっと…」
比較的、年若い3人は妙な連帯感を醸し出していた。年齢も近い(マーモン?)ということもあってか、ちょっとした愚痴大会である。
因みにこれはこのあともしょっちゅう行われており、話題はDVな父親(仮)の話やら、ベタベタうるさい母親(仮)のやら、
声の大きいアホな長男(仮)のこととか、つきることがなく3人の恒例となっていった。
そして、ともかく、今、彼女は、この黒い相棒を振るいたいということに夢中だった。
その心中を察したベルフェゴールが言った。
「……オレがなんとかしてやろうか?」
「めずらしいね、ベル。」
だって、殺せないってイライラするじゃん、と頭の上で腕を組みながら切り裂き王子は言った。
快楽殺人者ではないは、殺せないと、のところをあえて、無視してベルを期待の眼差しでみつめた。
この人なら本当にどうにかできる立場にいる人だ。もしかしたらもしかするかもしれない。
そんな彼女の様子もベルにとったら、いい気分だった。
(あはっ、先輩、泣くんじゃねぇ?)
そして、その場には、結局、結託してしまったらしい二人とこのあと起すスクアーロの行動を淡々と考えるマーモン。
本当に人外魔境のようだ。スクアーロの平穏はどこにある。
そして、ベルフェゴールはお決まりの台詞いって、書類にサインした
「だってオレ王子だもん!」
ついでにマーモンも。
そして、若い女が服を買いに行くかのごとく、春もほころぶ気分で彼女はAランク任務へと向かっていった。
そのあとを使命感に燃えた彼が追いかけてくるとも知らず。
願わくば、彼が早く彼女の正体に気づきますように。