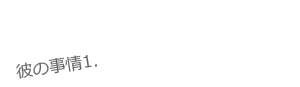
始めの印象は「何かの間違いだろう」という存在否定だった。
スクアーロはまず考える。ここは真っ当な仕事場ではない、その名も恐ろしい暗殺部隊であるはずだと。
しかし、瞬いても状況は変わらない。
視覚に異常はみられない。正常に働いている。
しかし、そこに見えるのは、子供を脱し切れていない幼く丸い輪郭にゆるい目元の人物だった。
「 と申します。」
日本の出だという、彼女は真新しい、彼には、おなじみの見慣れた制服を着ていたが、本来ストイックな真っ黒な制服は、
彼女が着ると、どこにでも居る事務職員に見えてくるのがなんとも、可笑しかった。
外見にはちらとも見せず混乱している彼を置いて彼女は人のいい笑顔で、ほわほわと腰を折る。
「今日から、よろしくお願いします。」
真っ当な挨拶だ。彼はくらくらした。ここはどこだ?暗殺部隊、ヴァリアーの本部だ。
自分は誰だ?暗殺部隊の幹部スペルビ・スクアーロだ。
彼女は、誰だ、…事務員?
「本日付けで、スペルビ・スクアーロ隊長の部下となりました。」
スクアーロは唯一の希望をもって、彼女から渡された資料に目を通す、
彼女の書類には、戦闘可という赤文字が記載されてあった。
矛盾は彼を混乱させる。事務だろ、どう見ても。
彼女はといえば、固まってしまった自分の上司に首を傾げ、書類に不備でもあっただろうか?と。
手元にない資料に記載したことを思い出そうと、考え込んでいるようだった。
そうして、暫くして彼がやっとフリーズから開放され、「あ゛、ああ…」と返答しかえし、彼女を見やる。
すると、彼女は再び、日本式でお辞儀を返してくる。
ほんとうに丁寧なお辞儀だった。
彼は最近日本へと行ったことがあったが、日本でも稀なほど、綺麗な楚々としたお辞儀だった。
そうして、彼はまた、資料に目を向けてみるのだった。
それが何週間か前のこと。
資料のミスか、と調べてみても、不備はなく、の入隊は滞りなく受理された。
そうして、初対面こそ、スクアーロは彼女のことを疑って掛かったが、ココはあのボンゴレの暗殺集団である。
人数は多く、いつのまにか彼は彼女のことを忘れていた。
彼女も最初も最初、名前なんて覚えられないほどの下っ端に位地していたため、任務を割り振られることはあっても、
それは、スクアーロが指示した、「南のゲートに5人回せ、」という無記名な任務で、個人を割り振ったのは別の人物だった。
どこか表のほそぼそとした会社の事務をしているような女の部下のことなんて、忙しい彼は、覚えている暇なんてなかった。
されに詳しく言えば、彼は唯我独尊な彼の上司と、個性豊かで協調性のない同僚達の間で、
彼の性格上からのいじられキャラとして確立しており、彼は多忙だったのだ。
今日も今日とて、彼は頭に被った酒の匂いに顔をしかめる。
彼の頭の中では、豪勢な椅子にどっかりと腰をかけ、机に足をのせ、ふんぞりかえる、数分前の上司の姿を思い浮かべては、
心のなかで、“あのクソボスが!!”と、本来の彼の声とおなじくけたたましく罵ってみている。
数分前、彼は今までの任務の報告に、久方ぶりに彼の上司に顔を出した。
しかし、ろくに目も合わさず「うるせぇ、」と飲みかけのグラスをザンザスに投げられた。
見事、額に当たった。もともとは素晴らしく美しかっただろうガラスのグラスは彼の石頭に砕かれて、琥珀色の酒とともに飛び散った。
あまりのことに彼は頭を反らせたが、そのまま反り返り、惨い扱いに抗議を叫んだ。
普通は流血し、救急車を呼ぶことだろうが、さすが習慣である。彼は慣れきっている。プロである。
彼は一通り叫ぶと、上司の二度目の「うるせぇ」に閉口した。赤い目に殺気が灯っていた。
殺したいやりたい仕打ちをうけたのは自分だ!と心の中で言い返しながら、大人しく報告書を提出した。
しかし、退室するとき、今度は酒ビンを投げられた。理不尽そのものである。
彼は息巻いていた。
任務を終えた自分に対する上司のソレも要因だったが、それ以上に今回の任務が彼には合わなかった。
今回、彼の任務は“交渉”。暗殺部隊とは言え、殺しばかりが任務ではない。
組織を円滑にするには、力だけではやっていけないのだ。
しかし、彼は、生まれ持っての戦闘狂で、頭で考えて、相手の思考や、画策の裏をつく、というのは、
戦いの中でが一番頭が閃くものだった。それを、生ぬるい嘘の笑みのなか、酒と食べ物に囲まれて、
誰が呼んだのかも分からない女にしなだれかかられながら、
あれやこれ、差し引きならないことを二枚舌で言い合う、“交渉”は性に合わなかった。
ではなぜ、幹部であり、それなりに任務を選べそうな彼がそんな任務をしなければ成らなかったのか。
彼の性分が上司に理解されていなかったのか、というわけではなく、その性分については周りも彼も、承知済みだったが、
それを差し引いても、幹部のなかで彼が一番、“交渉”に向いていたからだ。
今回の交渉は穏健に進めたい重要なことだが、だからといって
ボスであるザンザスがヴァリアーを空けるほどではない。(というかボス自身がメンドクサイとの仰せ)
では、幹部の誰かが、ということになったが、そこは、一筋縄にならない連中のあつまるヴァリアーの総本山である。
つまるところ、大多数が、交渉なんて無理だった。
例えば、切り裂き王子だったら、相手を切り裂くこと請け合い。
例えば、強欲な赤ん坊だったら、姿で舐められ、余計な手間をとる。
そうして一番まともそうなの、と言ったら、ほかの幹部の任務の期間も合わせて考えて、スクアーロになった。
―――表向きは。
余談にはなるが、
そのほかの幹部達から、押し付けられた感が否めないところが、彼のいいところだと思う。
“ふざけやがって!!”
その考えに同調するように、彼はズンズン、と廊下を歩く。
かったるい交渉中、なんど、相手が手のひらを返して自分に攻撃してくることを願ったことか。
本来あってはならないことだが、彼はそうなれば、一暴れできると人知れず思って笑っていたのだ。
比較的まともとはいえ、やはりヴァリアーである。
しかし、交渉は成功。任務としては万々歳。彼にとってはストレスの発散できない拷問であった。
彼はそのストレスは発散させるため、鍛錬に行くことにした。まずはこのむかむかを動いてどうにかする、というのだ。
まだ、歳若い頃から世界を股にかけて剣術の修行に明け暮れた行動派の彼らしいストレス解消法だ。
彼はわき目もふらずに歩く。
“一刻もはやく!”
彼はスピードを緩めず、石造りの角を曲がる。ここを過ぎれば、鍛錬所まで直ぐだ。
が、
「あ、」
「!」
彼はそこで、立ち止まることになる。
それが彼の事情の発端であった。
「すいません」
「悪いなぁ」
二人がぶつからなかったのは、反射神経の良さの賜物だったろう。お互いにあと一歩のところで、留まることができた。
スクアーロは一瞬、彼女に「なんだこの迷子」という感想を持った。しかし、よくよく見てみれば、見覚えがある。そういえば、
「お久しぶりです。」
彼女は、深々と腰を折る。相変わらず丁寧だ。
そう、彼女はあの事務員のような彼女だった。
今のの手には書類の束を抱えており、ますます、彼女は事務員風だ。
「ああ」
スクアーロは、やっと、この前入隊したどうみても堅気に見える女だということを思い出した。
その次の彼の素直な思いを述べるのならば、「生きてたのかぁ」だった。
ヴァリアーに弱者はいらない。そう掲げられていることを体言するように、入隊してまずは実戦あるのみなのだ。
入隊してこの時期まで、任務に一度も着かなかったという可能性はすくない。一回は必ず、任務についているはずだ。
ヴァリアーでは命を落とせばソレまで。そうして生き残り、幹部になっていくことで、人を使ったり、経験を生かせる職種についていく。
そして、それでも戦いから遠ざかる者はいない。そういうところなのだ。
だから、彼女にまた逢えたことは、忘れていたとはいえ意外だった。失礼ながら、絶対初任務で死んでると彼は思っていた。
彼はイラつきも忘れて彼女に問う。
「何やってんだ?」
「任務の報告書をほかの人の分も、まとめて上司に持っていくところです。」
この書類はまとめて順番にして、処理したほうが、手っ取り早いので、と当たり前のように彼女は言う。
スクアーロは思わず目をぱちくりとしてしまった。小さな気遣いだ。その小さな気遣いがここではこんなにも珍しい。
「そ、そうかぁ…」
「はい、」
彼らしくもなく、少しちぐはぐとしていると、「あ、」と彼女はなにか気がついたように微笑んだ。
「任務、お疲れ様でした。確か、大事な交渉の任務だったんですよね。先輩から伺っております。」
「あ゛あ…」
「お疲れさまでした。」
また、深いお辞儀をして、彼女は労わりと尊敬の念を込めて彼に微笑んだ。
それに、
スクアーロは驚愕し、その瞬間、硬直した。
え、なにこれ?
彼は感動していた。
かつて今まで、こんな風に任務を終えたあと、労わられることがあっただろうか―――いや、ない。
思わず反語法である。
いや、これが任務を終えた人間に向ける、本来の対応であるだろう。
間違っても昼間っからウイスキーを飲み、グラスやボトルを人に投げつけるわけではないだろうに。
しかし、確かにそうなのだ。
彼が今まで、どんなに血反吐を吐こうとも、一生着いて行くと豪語したはずの上司は、カス、と言い、
共に道を歩むはずの同士はダッセー、と笑ってくる。そういう人間関係なのだ。
いや、しかし、だからといって彼はわかっている。
あいつらが彼女のようなことをしたら、おもいっきり戦慄いて、顔の皮を剥いで本物かどうか確かめる必要があると。
ほかに彼の周りの人間といえば、彼の部下がいるが、彼の部下のほとんどは彼の激昂(自分の上司の我がままに対する、
部下への無茶振り)によって恐れられていたので、
彼に関わろうという人物はおず、こんな対応されたのは驚くことに、彼は初めてだった。
思わず、脳が混乱した。
彼は、一瞬で、固まり、考える。
ナニコレ。ナンダコレ。コレガ、ジャパニーズマゴコロ。そんな片言の日本語が心に浮かんだ。心身ともに混乱の極みであった。
上記のような人間関係で仕事をしていた屈強な彼に、彼女の言葉と態度は、直前のストレスに加えて、
長年蓄積した無自覚だった鬱屈に、クリティカルヒットを与えたのだ。
彼は少し引きつった顔で、どこか遠くを見つめて固まっていた。彼女はそんな彼を見つつ、首をかしげる。
疲れてるのかしら?とんな言葉が聞えてきそうだった。スクアーロは思う。
これは、とても、いい。
「……。」
「…あの、」
あまりの感動に、フラフラと彼女の肩に両手を置いて、彼は顔を伏せたまま考える。
与えられた情報に脳が空回りし始めた瞬間だった。
もしもの話だ。スクアーロは考える。
これからも任務から帰って来たら、こんな風に笑顔で「お疲れ様でした。」と労わられるとしよう。
もしもだ、野郎ばかりで汚い報告書をわかりやすいように、処理しやすいように、と振り分けて、渡されたとしよう。
もしもだ、疲れてきた、そんなベストタイミングに、「どうぞ、コーヒーです。」と温かいコーヒーを出された、としよう。
それはとても、
「いい。」
「はい?」
彼女を掴んだ力が強くなっていく。
(いいんじゃないか!?すごく!!やばくねぇ!?コーヒーとかやばくねぇ!?)
ヤバイのは彼の頭のなかだった。
そして、彼は考える。平凡そうな彼女はきっと、こんなところに居るべき人間じゃないだろうな。と。
「(きっと、こいつはなにか事情があって、ここに着たんだなぁ、)」ポスポスと彼女の肩を優しく叩く。
任務でも、半べそをかきながら逃げ回っているに決まっている。可愛そうになぁ。
スクアーロは自分の上司や同僚事情を棚に置いて、彼女を哀れむことにした。
鋭い目を精一杯優しくして、彼女を慰めるように肩を叩き続ける。
彼女は疑問ばかりの表情で、再度首をかしげた。
それが彼には、とても無知な子供の動作に見えて一層、眉を落とした。
そして、決心した。
「何かあったら、俺に言え!」
「…はぁ、ありがとうございます?」
コイツの任務に手を加えよう、と。
そして、自分の任務の後には必ず「お疲れ様」と言ってもらおう、と。
少しはこの自分の疲労が報われてもいいはずだ。とスクアーロは自らに言い訳をしつつ、
これからの根回しについて思考を巡らせる。言い訳をするわりには迷いがなかった。
そうして、スクアーロは彼女に背中を見せ、片手を振って退場した。後ろの彼女には見えないだろうが、どや顔である。
いいことしたぜぇ、と彼は満足気に、周りから見れば、いくらかクールに笑って見せた。
が、途中で通りかかった、とある王子に「うわ、にやついてるし、キモー」と言われ、その得意げな顔は崩れることとなる。
そして、熱の浮かされる、彼は忘れていたのだ。
ここはヴァリアー。ボンゴレ9代目直属、独立暗殺部隊本部である。
そしてそこに弱者は必要ないのであって、彼女は事務員のようで事務員でないのである。
そうして物語は開幕となったのだった。
(部下への無茶振りっていうのはアレです。10年後らへんのボスの肉がどうとかこうとかのらへん参考です。)
2011.02.10.反復法を反語法に修正。
間違えてました。ひぃ、恥ずかしい!指摘ありがとうございました!ありがたいです。m(_ _)m