本当は、届ける気なんてなかった。
地面にポツンと置かれたソレを何故が自分は引っつかみ、視線から逃げるようにアパートに逃げ帰ったあと、
飲まれそうになる激しい動悸にくらくらしながら、必死に考えていた。
あの人のことが知りたい。
あの人と話しがしたい。
けれど、どう考えようと自分の性分は曲げれそうになかった。
人は怖い。
恐る恐る開いた手のひらの中の蝶ネクタイを見て、自分はもしかしたら証拠が欲しかったのかも知れないと思った。
自分の芯のような冷静な部分を揺るがせた、先ほどの出来事の証拠。
常に頭のどこか冷めている自分が一色の歓喜に震えた瞬間の証拠。
いつもいつも、自分はどこか憂鬱だった。
テレビでやっていたお笑い番組で笑っているときも、映画で泣いているときも、先生に褒められているときも、
全部、気持ちが高まっていく直前で疑問と現状を投げかけ、感情をどこかセーブする。
それは、ずっと出口が見えないまま単調作業を続けるのと一緒だ。ずっと憂鬱。
私の冷静な部分は頼もしいけれど、いつも、ふとした瞬間、我に返らせて、私をずっと憂鬱にさせる。
けど、あの瞬間だけは、確かに全部忘れて、ただ純粋に「凄い」と思った。そして、私は知りたいと思った。
この蝶ネクタイの持ち主のこと。
だから、これを持って帰ってきたのかもしれない。
(こんなの、泥棒と一緒じゃない)
(返そうよ)
(でも、忘れたくない)
(あの人にとって大事なものかもしれないよ)
(なんでかバーテン服だったし)(こだわりがある人なのかも)
(でも何でバーテン服?)(似合ってるけど)(サングラスも)
(青かったね)(というか、なんであんなに細いのにあんなもの持てるの?)(というか受け止めてた人もいたよね)
(けどバーテン服の人は持ち上げて、なおかつ投げてるからね)(というか金髪だった)(もしかして外人?)
(名前は?)(黒人の人はシズオって言ってたけど)(苗字も気になる)(知りたい)(知りたい)(知りたい)
(アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!)
「あの人に・・・返さなくちゃいけないよね・・・?」
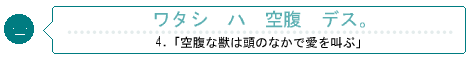
そうして、長い長い悩みの後、彼女は一歩を踏み出した。
それは、この町には色々な人が居て、沢山の歯車のように噛みあって回っているのを実感したからかもしれない。
離れたところで孤独に回り続ける、自分の小さな歯車も、どうにかしてこの町の一部になってみたいと。
例えば、人の上で跳ねる悪逆非道な男のように。 意外と薄情なような少女のように。
まだどんな人とも分からないライダーの人のように。 名前が神様のような少年のように。
板前の格好をした黒人のように。 踏まれた男のように。 酷いことを言われた少女のように。
まだ会ったこともない数々の人のように。
あの、バーテン服の男のように。
自分の評価も気にせずに、自分の速度で回ってみたいと、は声を上げた。
「あああ、あの!」
「?」
平和島静雄が振り向くと、そこには息も絶え絶えな少女が自分を見上げていた。
思わず首を傾げるのも無理はない。ここ数年、不本意ながら彼はマイナスな意味で有名で、
一般人は話しかけるどころか、近くにも寄ってこない。まぁそれは、自分の短い導火線を彼は重々理解してはいたから、
近付かれないことでこの厄介な性分が発動することは無いと、ホッとしてはいた。
拭いようのない孤独感は別として。
それなのに、目の前には、一般人という看板を背負っているような少女が一人。
自分に話しかけているのか?ちらりと辺りを見渡してしまう。
だが、近くにサイモンがいるほか、誰もそれらしき人は居ない。しかも目線は確実に自分。
「・・・俺?」
少女は首を痛めるような速度で頷いた。
首が鳴りそうな勢いでは頷いて、空回りしそうな口をキュッと閉め、言葉を考える、考える、考え・・・
「あの!すいません!昨日、自動販売機投げてましたよね?」
滑った。
目の前の男が、一回大きく瞬いたのを見たあと、彼女は、頭のなかで、頭を抱えた。
(開口一番がそれ!?)(いや、まず物事の始まりを、と思って)(順序は順序だけどソレ!?)
(ほんと馬鹿!)(テンパッてるし)(しかたないよ私だもん)(お前もだよ)(忘れてた)(むしろ忘れたい)
「行き成り、すいません・・・」
「いや、いいんだけど、何?」
いきなり昨日の“反吐が出そうなこと”に関係することを聞いたせいで、彼は少しイラついて、
言葉尻が怪しくなってしまった自分をなんとかなだめる。
どうやら、少女は昨日の出来事について、なにか用があるらしい。
チラつくノミ蟲の姿を頭の隅に追いやって、落ち着きのない少女を眺め、静雄は少し思う。
(自販のことを知ってるってことは、知ってるんだろうな、力のこと。)
―――――――それで、こんなにビクビクしてるのか?
今さっき潰した煙草の代わりが欲しくなった。
怯えられるのは慣れているが、だからといってこの空しさは無くなりはしない。
さっさと用事を済ませてほしい。暴力は嫌いなんだ。こんな力、使いたくてつかってるわけじゃない。
気を紛らわそうと、ポケットに入れたライターと煙草を出すために手を伸ばす。
すると、少女は何を思ったのか、地面に座り込んで、鞄を漁り始めた。
「おい、何してんだ?」
少し男がイラついている感じを感じ取った敏感なは、悲しくなった。
怒らせてしまった。
(そりゃそうだよね、見ず知らずだもん)(・・・。)(・・・。)(・・・。)
(・・・私なんて)(取るに足らない存在で)(世界は私無しだって回り続ける)
(私は)
「すいません、あの、昨日、これ、拾って・・・」
「もしかしたら、貴方のかもって、思って・・・」
鞄から出した少女の手には昨日、“反吐がでそうなこと”の際に無くしたと思っていた、自分の蝶ネクタイがあった。
驚いた。
未だに、しゃがみ込んでいる少女に合わせて彼はしゃがんで、その蝶ネクタイをまじまじと見た。
そして、眉を下げて申し訳なさそうにしている彼女を見る。
言いたいことは沢山あったが、言葉にすることは出来なかった。
ただ、わざわざ自分のもとへ息を切らせてまで、ネクタイなんて小さなものを届けにきた相手を見続ける。
まるで、焼き付けるように。
少女は、悲しそうにもう一度謝った。
「すいません、勘違い、でした」
無言な彼を誤解したは、自分の行いを後悔した。
彼女は彼の首元に着いている別の蝶ネクタイに気づいて、ますます身を縮めた。
今すぐこの場から走り去って仕舞いたかった。
けれど、それは、彼が彼女の手のなかにあった蝶ネクタイを受け取ったことで、全ては一変する。
「いや、確かに俺のだ。・・・ありがとうな」
ふわり、と何かが頭の上に乗った。
見なくても分かった、手だ。まるで羽根みたいに優しい手。
は恐る恐る顔を上げた。――――ああ、笑ってる。
(私は、)
(私は、何かを回せた、だろうか。こんな小さい歯車だけど)
***
「それは、二重人格のようなものってことですか?」
“冷静な獣”のことを聞き、前記の発言をした記者は、自分の発言を後悔した。
情報屋は笑っていた。―――その目は鋭く、気に入らないものを潰すような笑みで。
「そうじゃない。あの子は、それとは違う。すみません、口が過ぎるとは思いますが、
―――勝手にあの子を計るな。貴方なんかが。」
記者は口を閉じた。相手は自分より十は年下の男だったが、これはダメだ。
長年記者をやってきた自分の勘が言う。――――賢くあるなら口を閉じろ。愚は死が待っていると知れ。
「まあ、“冷静な獣”のせいであの子は常に憂鬱でしたから、その獣をぶっ壊したシズちゃんに懐くってのも分かる。
悔しいけど、あの子の常識を最初に打ち破ったのはあの化物だ。それは認める。ああ、ホント死んでくれないかなぁ。・・・。
でも、俺が気に入ってるのは“冷静な獣”でも、泡のような脳内会議でもなくて・・・。
本当のところ、俺もあの子のことは、計りかねてるんです。とても興味がある。
――――だから、知ったかでものを言われると腹が立つ」
「すみません」
「いいえ!」
情報屋は笑う。
そして、最後に嬉しそうに。本当に嬉しそうに記者に問いかけた。
「“愛情の反対は憎しみじゃない。無関心こそが愛情の反対だ”って知ってます?」
「あ、ああ・・・マザーテレサでしたか?」
「それなら、無関心の反対である、興味っていうのは愛情だ。」
「は、はぁ?」
「“知りたい”それは、愛の第一歩だと思いませんか?」
この取材は、後に、記者の入院なり、なんなりでお釈迦となり本となることはなかった。
ただ、回復した記者は思うのだ。
この取材のあと、情報屋は手の平を返したように、彼女のことを記事にしないほうがいい、と、
あの恐ろしい笑みで自分を脅してきた。いや、池袋の逆鱗と呼ばれる彼女のことが記事に書かれたとあったら
彼女の回りの人々が容赦ない、という、ただのアドバイスといった感じだったのだが、確かにあれは脅しに違いなかった。
ただ、彼は話したかっただけなのだ。彼女の事を。
“知りたい”と思うことが愛ならば、“知らせたい”というのも“知らせたいもの”への愛だろうか?
では、“知らせたくない”というのはなんだろうか。
それは、きっと、深い深い独占欲――――――。