今よりも一年ほど未来の話
池袋最強は誰か。
その取材をするうち、必ず上げられる名前に、“平和島静雄”という一人の男がいた。
この男が池袋最強なのか、と記事を取材する記者は確信を深めようと、彼の情報をほかの人物より深く求め始め、
そして、平和島静雄という人物をとりまく噂に、必ずと言って、ある“女性”の話が付属してくることに彼は気づいた。
隠者の賢者、喧嘩人形の歯車、池袋の逆鱗、という物々しい名前で呼ばれる影で、
対人恐怖症娘、シャイガール、ムツゴロウちゃん、などと呼ばれるその女性。
その女性は、平和島静雄とどういう関係なのか?
記者は紆余曲折を経て、新宿の情報屋と名乗る青年に“平和島静雄”に次いで、“彼女”について、
今まで調べた事柄と合わせて彼に訪ねた。
すると情報屋は、今までの笑み――――鋭く抉るような笑みを消し去り、
苦笑いのような、何かを思うような、
クシャリとした微笑を浮かべた。その笑みは、記者の頭に“池袋の逆鱗”という、彼女の呼び名を奇しくも思い起こさせた。
――――ここは新宿だが、彼はもともとは池袋の住人だったのだ―――――彼、折原臨也は今までで一番機嫌良く、彼女を謳う。
「ハハ、違う違う、あの子は――――――
***
―――――アレハ一体ナンナノデショウ?―――――
―――――ワカリマセン、ワカリマセン、ワカリマセン、―――――
―――――情報ガ不足シテイマス。―――――
―――――??―――――
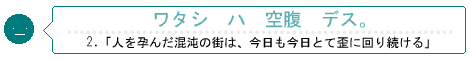
がいくら明日に恐怖しようと、時間は弁当を冷やしながら過ぎていく。
その夜、それに気づいた彼女が、冷たくなったご飯を急いで食べて、
丸まった足拭きマットを広げて敷いて、満足いく入浴を楽しみ、
そして、不安を胸に眠りについて、次の日の朝がきた。
今日は高校に入学して初めて、授業の始まる日だ。
余裕を持って起床したは少し考えこんで、ビニールでラミネート加工された真新しい教科書を鞄のスミに寄せて、
鞄の中にある小さなポケットのなかに、昨日から悩み続けている蝶ネクタイを入れた。
気休め程度にパチンとボタンを閉めて、鞄のファスナーを閉め、
制服のポケットに入れていたイヤフォンを首にかけて耳を塞ぐ。
制服に溶け込むような黒いエナメルコーティングされた銅線に繋がるipodから選んだ曲は、
あえて音が洪水を起したような曲だ。
通学中、彼女はこれを聞き続ける。
人が居るのに機械的故産まれる沈黙も、他人の雑談もは苦手だからだ。
町を歩いていると、町にも様々な表情があることが分かる。
特に昼と夜というのは、町は表情をがらりと変え、同じ道でも、夜歩けば、まるで違う道のようになり、人を迷わす。
朝の町は、人を機能的に流す、冷静なスーツの似合う人物のようで、
昼の町は、縁側で休憩を促す老人や猫のよう、
そして、夜の町は家路を急ぐ人にしな垂れかかり、「まだ帰らないで」とお願いする情熱的な人のよう。
町は、時間によって表情を変え、そして人間に色々な思いを訴えかける。
そして、それはも例外ではなく、彼女は、アパート近くのコンビニに置かれた、壊れかけのゴミ箱を見て、強く強く目を瞑った。
(あれはやっぱり、現実だった)
あれは昨日の夜、宙を舞った。
は出来れば肩に掛けている鞄から、ここで拾った蝶ネクタイを取り出したかったが、遅刻を心配して、
ゴミ箱を見て立ち止まっていた足をそのまま学校へと進める。その時間で遅刻するはずもないのだが、彼女は心配性なのだ。
洪水する音で頭を満たしながら、は溺れないように考える。
(あれは、確かにここで起こったことで)
(あれは、嘘ではなくて)
(あれは―――――確かに、壊した。)
(バラバラに、バラバラに)
(ああ、――――――怖いなぁ・・・)
うん、と頷く。
夜の町の残したわずかな表情は、彼女を町の混沌へと導いていく。
あるいは、その表情は、町が彼女にむけて出した歓迎の意だったのかもしれない。――――――池袋にようこそ、と。
***
授業は、一番初めということもあって、ほとんどがガイダンスや、教員や教員のための生徒達の自己紹介ばかりで、
本格的に内容に入ったのは数学と世界史ぐらいだった。
は授業の度に繰り返される自己紹介の繰り返しにぐったりしながら、
自分のほかの生徒の自己紹介を傾聴して、頭の中に情報を溜め込んだ。
自己紹介の度に1つネタのようなものを挟み込んでくる者。一時間目から生真面目にずっと同じ淡白な台詞を言い続ける者。
聞くだけでその人の人柄が窺えるような気がして、なかなか良さそうな自己紹介をする者の台詞を控えめに参考にしつつ、
は自分のクラスの雰囲気を掴むことに勤しんだ。
それはひとえに、このクラスに溶け込み、目立たないようにするための自己防衛の知恵だったが、彼女にとっては死活問題だった。
そのウチの一人、“竜ヶ峰帝人”という名前に彼女は妙な既視感を感じで、ぐったりしたまま考える。
(リュウガミネミカド・・・って神様みたいな名前だなぁ・・・ニギハヤミコハクヌシ・・・あ、全く似てなかった)
クラスメイトの一人の少年の物々しい名前に対して、そんなことを思っていると、ガイダンスの時間は通常の授業と違って、
なんとも早く過ぎ、委員会の顔合わせの時間のあと、時刻は放課後となった。
ここまでで1つ、彼女のチキンハートを揺るがす小さな問題が起こり、は憂鬱な吐息を零すことになったのだが、
それは今は置いておくことにする。ここではあまり必要な事柄ではない。
このあと起こったことのほうが、彼女にとって大きなできごとなのだ。
は今日も滞りなく緩やかに落ちていく遮光に包まれた廊下を歩みながら、下駄箱へと向かう。
その表情は浮かない。この廊下を歩くとき何時もこんな感じなような気がする。なにかこの廊下にはあるのだろうか。
しかし、その先の下駄箱で昨日のようなできごとは起きず、彼女はホッと思いながら校舎を出る。
たしかに、下駄箱では、何も起きなかった。
けれど、校門で何も起こらない、とは限らない。
西洋風の豪華な門を通り抜けたところで、その悪逆非道な光景は起こっていた。
「!!??」
は一瞬、下の人間のほうは人形かなにかだと思った。
それぐらい容赦なく人間が人間の上で跳ねていた。
地面に人が仰向けに倒れていて、その上で、コートのフードをヒョコヒョコさせながら、男が跳ねている。
「!!??」
は一度ならず二度も驚いた。え、なにあれ?なにやってるの?足は自然とその場で止まった。
その二人の人間の周りには、同じクラスの園原杏里と竜ヶ峰帝人がいて、と同じように呆然と跳ねている男を見ていて、
近くには個性的なヘルメットで表情の見えない黒いバイクに跨った人が立っている。
必死にはこの場に何が起こっているのか、このメンバーの関係性はなんなのか、考えてみたが、全く持って分からなかった。
そして、分からないまま、人の上で飛び跳ねていた男は、人を踏んだまま恭しく一礼して見せた。
「ありがとう」
は一瞬考えた。もしかしてあのフードの男が、倒れている男に「お前の上で跳ねさせてくれ」とお願いしたんだろうか?
しかし、その考えを直ぐに彼女は否定する。
礼を言った相手は男の下でピクリともしない―――――恐らく気を失っている。
そして、彼の目線は下の男ではなく、今にも、信じられない!と叫びだしそうな女の子に、だった。
最初は気づかなかったが、この子も関係者らしい。関係者に背中に羽をつけた女の子を追加して、は事の成り行きを見守った。男は続けるように口を開く。
「君は
―――俺が女の子を殴る趣味が無いからって、わざわざ男を用意してくれるとは、なんて殊勝な女の子なんだろう。
彼女にしたいけどゴメン、君、全然タイプじゃないから帰れ」
男がその台詞を言い放った瞬間、にはある種のカルチャーショックのようなものを感じた。
台詞の途中で逃げていく、追加したばっかりの女の子を気にすることも出来ず、
口に笑みを浮かべたまま辛辣なことを言う男に、
は釘付けだ。
人一倍怖がる彼女だからこそ、その男の言葉は、彼女にとっての衝撃だった。
(この人は怖くないんだろうか)
(人に嫌われること)
(人に評価されること)
(??)
場違いだが、彼女の胸に、男に対する尊敬の念のようなものが渦巻く。
そんなを他所に、校門のまん前の奇妙な集団は、お構いなしに話しを進めていく。
どうやら、跳ねていた男は、竜ヶ峰君に用があるらしく、黒いバイクの人もそれは同じようだった。
園原さんと別れた竜ヶ峰君を二人は追っていく。
残されたのは、園原杏里とと、地面で気を失っている踏まれていた男。
自分は全く関係ないと言っても、目の前で倒れている人間をそのままにしておくのは忍びない。
どうしよう、これ。
は悩む。
しかし、脱線。
「あ、」
もしかして、今こそ、園原さんと話すチャンスじゃないか?
昨日の下駄箱での出来事とくらべれば、今は友達を作るいいチャンスだ。
「あ、あの園原さん!!」
今、話しかけるフレーズは沢山ある。
分かち合いたい感想も、訊きたいことも沢山、沢山、
はここ最近なかった心地よい会話を楽しもうと隣に立っていたはずの園原杏里に話しかける、
が、
園原杏里は、今まであった奇怪な出来事など知らぬとでも言うように、道の向こうにある角を曲がり、姿を消す寸前だった。
当然の声は届かない。またもや、そのまま、彼女は姿を消す。
「・・・あれ?」
残されたのは、と、踏まれて意識のないどこの誰だかもわからない男だけ。
「・・・・・・。」
はこの奇怪な出来事の尻拭いが、まったく関係ない自分に巡ってきたことを知った。
「・・・。」
――――――押し付けられたは走る。さっきまで委員会で集合していた保健室へと。先生を呼んでくるために。
そう、彼女は昨日の委員決めの時、目立たず、競争率も低い、保険委員を選んでその任へとついたばかりだった。
走る間、彼女は考える。
不遜な男、意外と薄情な少女、感情の読めない無口なライダー、
その人々に囲まれていた、物々しい名前だが普通そうな少年――――――――
壊れる壊れる
(ばらばらと、ばらばらと、)
(怖い)
(怖い・・・かな?)
(そうかな?)
―――――ああ、騒ぎ始める。
町は回り続け、少女の物語も回り始めた。きっと町は彼女を飲み込んだのだろう。
回る、
回る、
歪に、
歪に、